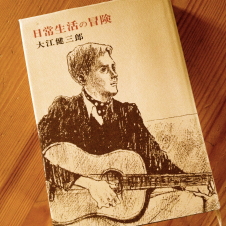DAYS_
伊丹十三をなきものにすること。
January 12, 2015 /
佐賀関から出発するフェリーへ車ごと吸い込まれたのは、元日の朝でした。前日からの強い低気圧で海はかなり荒れていて、おまけに寒い。あの人は船酔いの薬を飲んで寝たフリを決め込んでいるので、仕方なくひとりでデッキをうろうろ。強風もなんのその、たったの1時間半で四国は佐田岬の先端の三崎へ到着。 デンマークの古い陶器を探して、冬のバルト海をボーンホルム島へ渡ったのはいつだったか。去年はネイテイブ・アメリカンのクラフトを求めてカナダのヴァンクーバー島へも渡ったっけ。ガーミンという小さなGPSさえあれば、海をわたって島に上陸し、なんなく目的地へたどり着けることを知ったわけです。なんといっても、遠くの島影がだんだん近づいてきて、ゆっくり岸壁に着岸するときがいい。飛行機のように、気が付くと運ばれてしまっているのではなく、じわっとたどり着いた感が断然いいのです。
デンマークの古い陶器を探して、冬のバルト海をボーンホルム島へ渡ったのはいつだったか。去年はネイテイブ・アメリカンのクラフトを求めてカナダのヴァンクーバー島へも渡ったっけ。ガーミンという小さなGPSさえあれば、海をわたって島に上陸し、なんなく目的地へたどり着けることを知ったわけです。なんといっても、遠くの島影がだんだん近づいてきて、ゆっくり岸壁に着岸するときがいい。飛行機のように、気が付くと運ばれてしまっているのではなく、じわっとたどり着いた感が断然いいのです。
今回の旅の一番の目的は、松山にある「伊丹十三記念館」を訪れることでした。『ロードジム』という映画で”英語が喋れる国際派俳優”として脚光を浴びた彼を知ったのは、多分中学生の頃だったか。その後『ヨーロッパ退屈日記』というエッセイを読んだのは大学生になった頃かも。何が何でもスパゲッティをアルデンテで食べたくなりました。そして大人になって映画『お葬式』を観てしまったわけです。まるで小津とゴダールが合体したかのような、事件でした。ユーモアをまぶしたサタイアと、自由で乾いたスタイルはまったく彼の独壇場だったと思います。
中村好文氏が設計した「伊丹十三記念館」は、中庭を囲む正方形の端正な建物で、一瞬アールトが手がけた町役場を思い出しました。展示室には、十三の名前にちなんだ13のコーナーが設けてあり、商業デザイナー、俳優、エッセイスト、雑誌編集者、映画監督を含めた実に多彩な才能を、オリジナルな資料でじっくりとたどることが出来ます。なかでも今回興味深かったのはテレビ人・伊丹十三でした。特にテレビマンユニオンと一緒に制作したドキュメントっぽい番組群は、いまさらのように衝撃的でした。実験的だから自由、おまけにアナーキーな表現が民放でオンエアされていた1970年代がうらやましくなります。ちょうど会場で流れていたのは『遠くへ行きたい』という番組。信州の山奥の村を訪ねて、古老の話を聞くのは宮本常一。生涯に渡り日本各地をフィールドワークし続け、膨大な記録を残した民俗学の人をフィーチャーしているのです。つい最近ですが、「民具」と呼んだ生活用具や技術を手がかりにして、ニッポンという国を「大和民族」ではない、様々なオリジンを持つ「多層的な人種」とみなす彼の著作にハマりかけていたボクは、おもわず画面に釘付けにならざるを得ませんでした。初めて聞く宮本常一の肉声は、笠智衆そっくり。まるで宮本の代表作のタイトルである『忘れられた日本人』そのままの不思議なイントネーションでした。
あくまでも個人的な思いですが、伊丹十三はセルジュ・ゲンスブールです。マルチな才能を使い、挑発的な表現でもって、らちもない世間をサクッと生き抜いた、筋金入りの異能な人でした。したがって、伊丹十三をなきものにすることは、まったく不可能なのです。